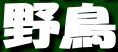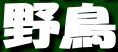|

こうたろうは、いつも双眼鏡と野鳥観察ハンディ図鑑(日本野鳥の会発行)を手にして野鳥観察へと出かけます。しかし、残念ながらまだまだその観察眼は???です。
観察を始めた頃(1、2年生の頃)は、大人と違って妙な先入観がないために、凡その外見と声で判断して「珍鳥」の名を口にしてくれることがよくありました。さすがに最近は少なくなりましたが、結構楽しませてくれます。また、意外に野鳥観察を始めたばかりの人にとっては、こうたろうの説明が分かりやすかったりします。
この野鳥図鑑は、野鳥観察ハンディ図鑑(日本野鳥の会)を利用させていただいて作成しました(というか解説文は丸写しですが…)。分類については、私たちの観察に基づいた(?)、「この場所でよく見るなぁ」という独断と偏見で設定しましたのでご了承ください。尚、デジカメの写真は素人の私(父)が撮影したものですから、悪しからず…
※記号などの説明はこのページの最後を参考にしてください
 
1.身近な鳥(家) 5種類
野鳥観察ハンディ図鑑に、身近な鳥とは「ほぼ、全国的に、人の生活環境に近い場所でも見られる鳥」と紹介されているが、なかなかどうして初心者には見つけにくいものです。その点、この鳥たちは、私たちと生活を一緒にしているといっても良いぐらいで、野鳥に興味のない人でも知っている超ポピュラーな鳥ではないでしょうか。
 スズメ キジバト ヒヨドリ ツバメ メジロ スズメ キジバト ヒヨドリ ツバメ メジロ
2.身近な鳥(公園&里山) 14種類
野鳥に興味を持ち始めて、双眼鏡首から提げ、図鑑を片手に近くの公園や田圃、里山に出かけたときに初めて知る鳥たちです。素早く樹上を移動する鳥、飛んでいる鳥を双眼鏡に入れられるようになったころから、遭遇する鳥たち一度覚えてしまえば、結構、家の周りにいたりなんかします。
 シジュウカラ カワラヒワ ホオジロ コゲラ モズ ドバト ヒバリ ウグイス シジュウカラ カワラヒワ ホオジロ コゲラ モズ ドバト ヒバリ ウグイス
シロハラ ツグミ ジョウビタキ ヤマガラ イカル エナガ
3.水辺の鳥(泳いでいる鳥) 5種類
野鳥観察を始めたばかりの頃には、とってもありがたい存在でした。何故かって?。とっても観察しやすいじゃあ~りませんか。しかし、暖かくなると、みんな北へ帰っちゃいます。異種やアヒルとの交雑が多いためか、観察技術の未熟さか、「あれは何やろう」と首を傾げる鳥が多くて困っています。
 カイツブリ コブハクチョウ ヒドリガモ ハシビロガモ マガモ カイツブリ コブハクチョウ ヒドリガモ ハシビロガモ マガモ
4.水辺の鳥(歩いている鳥・飛んでいる鳥) 18種類
水辺をチョコチョコ歩く鳥、水の中に突っ立ってキョロキョロしている鳥、水の上をスイスイ飛んでいる鳥。ユーモラスで楽しげなアクションに比べて、なぜだかみんな目が怖~い(!?)
 コサギ ダイサギ アオサギ バン オオヨシキリ トビ アマサギ カワセミ コサギ ダイサギ アオサギ バン オオヨシキリ トビ アマサギ カワセミ
イソシギ コチドリ ハクセキレイ セグロセキレイ キセキレイ イソヒヨドリ
ユリカモメ カモメ ケリ ゴイサギ
| スズメ |
スズメ目ハタオドリ科 L14.5 W22.5 |

打上川治水緑地 |

幼鳥(自宅) |
|
人家付近のみで見られる。ほおに黒い斑(幼鳥ではうすい)。
歩くときは両足を揃えて跳ねる。チュン、ジジなどさまざまな声を出す。
ヨーロッパで人家付近にいるのはイエスズメ(雄はスズメに似て額が灰色。近年日本でも発見された)で、スズメは郊外にいる。留鳥といわれるが、その年に生まれた鳥は秋に移動すると思われる。
<求愛>春先、雄はそらした体を上下して、雌に求愛する。
<交尾>雌が姿勢を低くすると、雄が上に乗る。
<砂浴び>スズメ目の多くは水浴びをする(ヒバリは砂浴び)が、スズメは水浴びも砂浴びもする。
<羽づくろい>鳥はくちばしで羽の手入れをしながら、腰から出る脂を塗る。
<頭かき>スズメ目のほとんどの鳥は、下げた翼の間から足を出して頭をかく。この方法は「翼ごし頭かき」と呼ばれる。
 (雀)シュシュという鳴声と“メ”(群れ鳥のこと)から、「スズメ」 (雀)シュシュという鳴声と“メ”(群れ鳥のこと)から、「スズメ」
 一番人間の近くにいてるのに、人間にはぜんぜん慣れへんねんなっていつも不思議に思うねんけどなんでかな。子スズメはあんまり飛ばれへんから近づいても逃げへんけど、いたずらされたり、ネコやカラスに食べられへんかちょっと心配です。 一番人間の近くにいてるのに、人間にはぜんぜん慣れへんねんなっていつも不思議に思うねんけどなんでかな。子スズメはあんまり飛ばれへんから近づいても逃げへんけど、いたずらされたり、ネコやカラスに食べられへんかちょっと心配です。
 |
| シジュウカラ |
スズメ目シジュウカラ科 L14 |

淀川水系 |
|
白いほお、胸から腹にネクタイ模様(太い方が雄)
市街地から、山地まで。チッチーなどの細い声はシジュウカラ科に共通しているが、ジュクジュクと濁った声は独特。求愛給餌をする
S細い声でツーピーやツツピーを繰り返す。
 (四十雀)地鳴きの「ジュクジュク」と小鳥を意味する「カラ」 (四十雀)地鳴きの「ジュクジュク」と小鳥を意味する「カラ」
 一番いろんなところに居てる野鳥って何かの本に書いてたけど、万博公園や山田池公園にはスズメよりたくさん居てるし、山に行ったときも一番多いから、そうかなと思った。テレビのドラマに使われている鳥の声は、シジュウカラが多いと思う。 一番いろんなところに居てる野鳥って何かの本に書いてたけど、万博公園や山田池公園にはスズメよりたくさん居てるし、山に行ったときも一番多いから、そうかなと思った。テレビのドラマに使われている鳥の声は、シジュウカラが多いと思う。
 |
| カワラヒワ |
スズメ目アトリ科 L14 |

打上川治水緑地 |
|
肌色で太めのくちばし、翼と尾に黄色の斑
九州以北。林、草地、農耕地川原に普通。市街地では空き地でタンポポなどの種子を食べる。樹上に細い草をつづった小さなおわんの形の巣をつくる。黄斑が飛ぶと目立つ。M尾。高い声でキリリリと鳴く。
Sビィーンと濁った声も出す。
 (河原鶸) 河原にすむヒワ。ヒワは「ひ弱い」の意。 (河原鶸) 河原にすむヒワ。ヒワは「ひ弱い」の意。
 チリリリリって鳴きながら飛んでいるのをよく見る。オスは電線とかに止まって、ビィーンってさえずっている。羽を開いたり閉じたりして飛んでいるのが他の鳥とは違う。タンポポとかの花の種が好き。黄色い羽が目立つのですぐに分かる。スズメに混ざって田んぼにいてる。 チリリリリって鳴きながら飛んでいるのをよく見る。オスは電線とかに止まって、ビィーンってさえずっている。羽を開いたり閉じたりして飛んでいるのが他の鳥とは違う。タンポポとかの花の種が好き。黄色い羽が目立つのですぐに分かる。スズメに混ざって田んぼにいてる。
 |
| キジバト |
ハト目ハト科 L33 W55 |

ラポール枚方前 |

打上川治水緑地 |
|
翼や背に茶色のうろこ模様、首にしま模様
市街地から山地まで(北海道では夏鳥)。ほぼ一年中繁殖しており、雌雄2羽で見ることが多い。3羽では親子の可能性がある。幼鳥は首のしま模様が薄い。オスはデッデ、ポッポーと低い声で繰り返し鳴く。樹上に枝を集めて粗雑な巣を作る。
<ディスプレイフライト>雄は巣の周りをタカのように滑空して飛ぶ。なわばり宣言の意味があるらしい。
 (雉鳩)色彩がキジの羽に似ていることから (雉鳩)色彩がキジの羽に似ていることから
 だいたいツガイでいることが多いオスとメスが仲のいい鳥。うちの家の庭にもよくやってくる。あまり人を怖がらない。この前、細い木の間に入って、出られなくなっていたりするけっこうあわてもの。羽の色とかとてもきれいなので割りと好きです。鳴声はポッポッポッではなく、デッデ、ポポーって感じです。 だいたいツガイでいることが多いオスとメスが仲のいい鳥。うちの家の庭にもよくやってくる。あまり人を怖がらない。この前、細い木の間に入って、出られなくなっていたりするけっこうあわてもの。羽の色とかとてもきれいなので割りと好きです。鳴声はポッポッポッではなく、デッデ、ポポーって感じです。
打上川治水緑地を散歩していたときに見つけた。見つけたのは冬やったんですぐ分かったけど、子育てのときは、葉っぱがいっぱいあってちゃんと隠れているんやと思う。なんかあんまりきれいな巣とちゃうなあと思った。
 |
| ドバト |
ハト目ハト科 L33 |

打上川治水緑地 |
|
灰色のものが普通だが、さまざまな色や模様がある
飼われていたハトが野生化したもので、野鳥には含まれない。市街地に多く、キジバトより群れになる性質が強い。建造物に巣を作る。
<ドバトの求愛>雄は首を上下し、尾を広げてメスに求愛する。一年中見られる。
 (堂鳩)神社のお堂などにすみついているので堂鳩(ドウバト)から。 (堂鳩)神社のお堂などにすみついているので堂鳩(ドウバト)から。
 公園とかに集団でおって、散歩している人から餌をもらっている。いろんな色のドバトがおるけど、種類は一緒らしい。もともと人に飼われていた鳥で、野鳥とは違う。ポッポッポッと鳴く。 公園とかに集団でおって、散歩している人から餌をもらっている。いろんな色のドバトがおるけど、種類は一緒らしい。もともと人に飼われていた鳥で、野鳥とは違う。ポッポッポッと鳴く。
 |
| ヒヨドリ |
スズメ目ヒヨドリ科 L27 |

打上川治水緑地 |

幼鳥(自宅) |
|
ピーヨまたはキーヨと甲高く、伸ばす声
市街地から山地の林。秋に南西方向に移動する群れが見られる。目の下後方は茶色。興奮すると、頭の羽毛を逆立てる。ピーヨロイロピなどと鳴くこともある。
 (鵯)稗を食べる鳥(ひえどり)から転じて。ただし、ヒヨドリは稗を食さないので、ヒィーヨという鳴声からつけられたという説の方が有力。 (鵯)稗を食べる鳥(ひえどり)から転じて。ただし、ヒヨドリは稗を食さないので、ヒィーヨという鳴声からつけられたという説の方が有力。
 一年中家の近くにいてるグループと、よそからわたってくるグループがいてるみたい。よく見たら色も少し違うみたいやけど、種類は一緒なんかなあ。餌台の果物を、メジロとかから横取りして食べてしまうから、あんまり好きじゃない。飛び方は波みたいに飛ぶので、すぐ分かる。
一年中家の近くにいてるグループと、よそからわたってくるグループがいてるみたい。よく見たら色も少し違うみたいやけど、種類は一緒なんかなあ。餌台の果物を、メジロとかから横取りして食べてしまうから、あんまり好きじゃない。飛び方は波みたいに飛ぶので、すぐ分かる。
ヒヨドリの巣をおとうさんが、庭の桑の木の枝をきっていたときに見つけた。小さいから、はじめはよく来ていたメジロかカワラヒワかなと思ったけど、どうやらヒヨドリらしい。巣の外は小さな木の枝で、中は草の葉っぱやビニールヒモでできていた。
それとこの前、うちの庭に幼鳥がいた。親鳥が近くで見守っていて、幼鳥に近づくと、大きな声で警戒音を出していた。襲われそうで怖かった。
 |
| モズ |
スズメ目モズ科 L20 |

深北緑地 |
|
黒い過眼線(雌は褐色)、長めの尾を回すように振る。
林の周辺、農耕地、河川敷などのやや開けた環境で繁殖。北海道や山地では、秋冬に団地や低地に移動。キチキチと続けたり、ジュン、ジュンなどと鳴き、秋にはキーィ、キーィと甲高く鳴く。
 (百舌)他の鳥の鳴きまねをするので百舌「ももした」から転じて。 (百舌)他の鳥の鳴きまねをするので百舌「ももした」から転じて。
 木のてっぺんにとまって、カン高い声で鳴く。他の鳥の鳴きまねが得意で、ホオジロやウグイスのマネをしているのを聞いたことがあるけど、だまされそうになった。小鳥も食べるので、モズがやってくると近くにいる小さな野鳥たちは逃げだす。 木のてっぺんにとまって、カン高い声で鳴く。他の鳥の鳴きまねが得意で、ホオジロやウグイスのマネをしているのを聞いたことがあるけど、だまされそうになった。小鳥も食べるので、モズがやってくると近くにいる小さな野鳥たちは逃げだす。
 |
| ホオジロ |
スズメ目ホオジロ科 L16 |

♂淀川 |

♀淀川 |
|
腹が茶色、チチッまたはチチチィと短く続けて鳴く
屋久島以北。林の周辺、農耕地、河川敷などのやや開けた環境にすむ(北海道では主に夏鳥で少ない)。よく草地で採食する。スズメより長めの尾で、顔に黒白の模様(雌は黒い部分が褐色)
S木のこずえなどの目立つところで、細い声で早口にチョッピーチリーチョッチーツクなど。
 (頬白)頬が白いから「ホオジロ」。実際に白いのは頬よりも下の部分で、あまり目立たない。 (頬白)頬が白いから「ホオジロ」。実際に白いのは頬よりも下の部分で、あまり目立たない。
 はじめは、スズメと似ているなって思ったけど、今はだいたい見分けがつく。オスとメスもよく見たら、顔のもようが違う。「源平つつじ白つつじ」という聞きなしが有名だけど、写真のホオジロは、そこまで上手に鳴いてなかった。「源平つつじ、白つ…」くらいやった。 はじめは、スズメと似ているなって思ったけど、今はだいたい見分けがつく。オスとメスもよく見たら、顔のもようが違う。「源平つつじ白つつじ」という聞きなしが有名だけど、写真のホオジロは、そこまで上手に鳴いてなかった。「源平つつじ、白つ…」くらいやった。
 |
| ウグイス |
スズメ目ウグイス科 L♂16 ♀13 |

淀川 |
|
低いやぶの中で、チャッ、チャッと鳴く(地鳴き)
林のやぶで繁殖し、秋冬は根雪のない地域のやぶにすむ。
Sホーホケキョのほか、ケキョケキョを繰り返すこともある。
 (鶯)春になると奥山から出てくるので「奥出づ」から転じて。「春告鳥」「花見鳥」の別名もある。 (鶯)春になると奥山から出てくるので「奥出づ」から転じて。「春告鳥」「花見鳥」の別名もある。
 野鳥のことをあんまり知らんかったときは、もっと緑色やと思っていた(メジロくらい)。けど、この前淀川で見たウグイスは、目の前で鳴いてなかったら、ウグイスと思われんほど変な色をしていた。このウグイスは、とっても上手に鳴いていた。 野鳥のことをあんまり知らんかったときは、もっと緑色やと思っていた(メジロくらい)。けど、この前淀川で見たウグイスは、目の前で鳴いてなかったら、ウグイスと思われんほど変な色をしていた。このウグイスは、とっても上手に鳴いていた。
 |
| ヒバリ |
スズメ目ヒバリ科 L17 |

淀川 |
|
足を交互に出して歩く。時々冠羽が立って見える。
九州以北にすむが、積雪のある地域では秋冬に暖地へ移動。飛び立つ時にビルッと鳴く。
S上空で、ピーチュルピーチュルなどと長く複雑に続ける。
 (雲雀)晴れた日に上空でさえずることから「日晴れ」。鳴声からついたという説もある。 (雲雀)晴れた日に上空でさえずることから「日晴れ」。鳴声からついたという説もある。
 図鑑で見たら、カシラダカと似てるなって思ったけど、くちばしが長い。ピチピチって鳴きながら、空で羽ばたいているところをよく見るので、こんなかわいい顔をしてるって知らなかった。 図鑑で見たら、カシラダカと似てるなって思ったけど、くちばしが長い。ピチピチって鳴きながら、空で羽ばたいているところをよく見るので、こんなかわいい顔をしてるって知らなかった。
 |
| ツバメ |
スズメ目ツバメ科 L17 W32  |

自宅付近 |
|
燕尾。上面が一様に黒い。
主に九州以北に飛来(北海道では少数)。建造物に泥を材料にしたおわん型の巣をつくる。雄の尾は雌より細長い。チュピィなどと鳴く。
Sチュチュビチュチュビジクジクビーと最後が濁る。
 (燕)土をくわえて運ぶので「土喰み(ツチバミ)」、古名の「ツバクロ」も「土喰黒女(ツチバミクロメ)」に由来する。 (燕)土をくわえて運ぶので「土喰み(ツチバミ)」、古名の「ツバクロ」も「土喰黒女(ツチバミクロメ)」に由来する。
 家の近くでもたくさん飛んでるけど、うちの家には巣を作ったことがない。何か基準があるんかなあ?ツバメが日本に来るのは5月ごろかなって思ってたけど、3月には来てるって知ってちょっとびっくりしています。でも、あんなに早く飛びながら、上手に虫を取るのはすごいなあ。 家の近くでもたくさん飛んでるけど、うちの家には巣を作ったことがない。何か基準があるんかなあ?ツバメが日本に来るのは5月ごろかなって思ってたけど、3月には来てるって知ってちょっとびっくりしています。でも、あんなに早く飛びながら、上手に虫を取るのはすごいなあ。
 |
| オオヨシキリ |
スズメ目ウグイス科 L18  |

打上川治水緑地 |
|
スズメより大きく、にぎやかなさえずり。
ヨシ原に飛来する。北海道では南部のみで少ない。
Sギョシギョシ、ケケチケケチなど、早口の大声で、長く続け、夜も鳴く。同じ夏鳥のコヨシキリは北海道に多く飛来し、ヨシ原以外の乾燥した草地にもすむスズメより小さい鳥。
 (大葦切)「葦の葉を切って中の昆虫を食べる」「葦の葉を切り裂くように鳴く」ので、葦切。また、「葦潜り(ヨシクグリ)」が転じたなど諸説。 (大葦切)「葦の葉を切って中の昆虫を食べる」「葦の葉を切り裂くように鳴く」ので、葦切。また、「葦潜り(ヨシクグリ)」が転じたなど諸説。
 笑っているような、楽しそうな鳴き方をする。鳴くときは、大きな口をあけているので、面白い顔になる。治水緑地にはそんなにいてへんけど、淀川では何百羽もいて、いっせいにさえずってんねんから頭が痛くなるほどやった。 笑っているような、楽しそうな鳴き方をする。鳴くときは、大きな口をあけているので、面白い顔になる。治水緑地にはそんなにいてへんけど、淀川では何百羽もいて、いっせいにさえずってんねんから頭が痛くなるほどやった。
 |
| コゲラ |
キツツキ目キツツキ科 L15 |

山田池公園 |
|
スズメ大で、ギーと戸がきしむような声。
太い木や古い木があれば、住宅地や公園でも見られるようになってきた。ギーという声の後にキッキッキッと続けて鳴くこともある。シジュウカラ科の群れの後に1~2羽でいることがある。
 (小啄木鳥)ケラは、木の中の虫ケラをつついて食べるので「ケラツツキ」「キツツキ」から由来。 (小啄木鳥)ケラは、木の中の虫ケラをつついて食べるので「ケラツツキ」「キツツキ」から由来。
 キツツキの仲間で一番小さい鳥。木の周りをくるくる回って、上がったり下がったりしながらエサを探している。ギィーっていう声で鳴くのですぐに分かる。公園や山の中だけでなく、家の木にもよく来る。 キツツキの仲間で一番小さい鳥。木の周りをくるくる回って、上がったり下がったりしながらエサを探している。ギィーっていう声で鳴くのですぐに分かる。公園や山の中だけでなく、家の木にもよく来る。
 |
| トビ |
タカ目タカ科 L59~69 W157~162 |

淀川 |
|
カラスより大きく、長めの角尾(×他のタカ科)。
屋久島以北。水辺から山地まで、もっとも普通に見られるタカ。生きた動物を襲うことが少なく、魚や死んだ動物などを食べ、ゴミ捨て場にも集まる。群れる、角尾(M尾に見えるものもいる)、比較的ゆっくりはばたく、色が濃い、他の鳥があまり恐れないなどが他のタカとの識別に役立つ。ピーヒョロロと鳴く。
 (鳶)空を高く飛ぶことから、飛び(トビ)。 (鳶)空を高く飛ぶことから、飛び(トビ)。
 ピーヒョロロと鳴いて、ゆっくり飛んでいることが多い。他のタカと違って、鳥は恐れないと図鑑に書いてあるが、カッコいいと思う。尾羽がMの字になっている。僕の小学校の校歌に出てくるのに、今は学校の周りにはいない。
ピーヒョロロと鳴いて、ゆっくり飛んでいることが多い。他のタカと違って、鳥は恐れないと図鑑に書いてあるが、カッコいいと思う。尾羽がMの字になっている。僕の小学校の校歌に出てくるのに、今は学校の周りにはいない。
 |
| コサギ |
コウノトリ目サギ科 L61 |

(冬羽)天野川 |

(夏羽)天野川 |
|
黒いくちばしが冬も黒く、足の指が黄色。
本州から九州の林で集団で繁殖し、各地の水辺で見られる。カラスほどのサイズだが、白いサギでは小型。繁殖期の一時期に足と目元がピンク色になる(婚姻色)。活発に歩き(=アマサギ)、浅い水辺では、足をふるわせるようにして魚を取ることがある。時々グアーとしわがれ声を出す。
 (小鷺)サギは、声が「騒がしい」、あるいは白い羽根が「さや(清や)けき」鳥からであることから。 (小鷺)サギは、声が「騒がしい」、あるいは白い羽根が「さや(清や)けき」鳥からであることから。
 白いサギの中で一番小さいけど、夏になるとはえてくる背中のかざり羽と、頭の冠羽がおしゃれだと思う。足の指が黄色いので、飛んでいるときはすぐに見分けがつく。飛ぶときは、首を折りたたんで飛ぶ。
白いサギの中で一番小さいけど、夏になるとはえてくる背中のかざり羽と、頭の冠羽がおしゃれだと思う。足の指が黄色いので、飛んでいるときはすぐに見分けがつく。飛ぶときは、首を折りたたんで飛ぶ。
夏羽のコサギと冬羽のコサギが一緒におったんを、オスとメスのツガイやと思ってた(お父さんもそう思ってた)けど、博物館の和田さんに「もういっぺん調べたら」って教えてもらいました。図鑑で調べたらオスもメスも同じようにかざり羽がはえるので、見分けるのが難しいことが分かりました。
 |
| ダイサギ |
コウノトリ目サギ科 L89 |

蔵王池 |
|
最も大きな白いサギで、極端に首が細長い。
コサギ同様さまざまな水辺で見られるが、九州から本州にかけて夏鳥として飛来し繁殖するものと、冬鳥として飛来するものがある。一般に体が大きなものほど動きが少なくなる傾向があるが、コサギのように足早に歩きまわるよりも、より深い水辺をゆっくり歩くか、じっと立っていることが多い。ゴワーと鳴く。
 (大鷺)大型のサギ(※コサギの項目を参照)であることから。 (大鷺)大型のサギ(※コサギの項目を参照)であることから。
 白いサギの中では一番大きい。コサギみたいに川の中を歩き回らんと、ジッとして餌を探していた。写真は6月に見たやつやけど、くちばしがまだ黄色かった。 白いサギの中では一番大きい。コサギみたいに川の中を歩き回らんと、ジッとして餌を探していた。写真は6月に見たやつやけど、くちばしがまだ黄色かった。
 |
| アオサギ |
コウノトリ目サギ科 L93 |

寝屋川 |
|
背が灰色をした、最も大きなサギ。
九州以北の林での林で集団繁殖し、各地の水辺で見られる。北日本では秋冬に暖地に移動するものが多い。正面からは白く見えるが、横、後ろからは灰色に見える。成鳥では首が白く、頭に黒い冠羽があるが、若い鳥では首や冠羽の部分がぼやっとした感じ。立ったまま翼を半開きにして、日光浴をする。
 (蒼鷺)背が灰青色のサギ(※コサギの項目を参照)であることから。 (蒼鷺)背が灰青色のサギ(※コサギの項目を参照)であることから。
 一番大きなサギ。寝屋川では一番数が多いんとちゃうかなと思う。ゴアーと大きな声で鳴く。3年ほど前に、近くの池で30くらいのコロニーを作っていた。左の写真のアオサギは、少し小さい気がしたので、多分まだ若い鳥やと思う。 一番大きなサギ。寝屋川では一番数が多いんとちゃうかなと思う。ゴアーと大きな声で鳴く。3年ほど前に、近くの池で30くらいのコロニーを作っていた。左の写真のアオサギは、少し小さい気がしたので、多分まだ若い鳥やと思う。
 |
| コブハクチョウ |
カモ目カモ科 L142 |

打上川治水緑地 |
|
赤みのあるくちばしで、付け根に黒いこぶ。
各地の池で飼われており、野生化したものが見られ、繁殖していることもある。オオハクチョウやコハクチョウより、尾が長くとがって見える。あまり鳴かない。
 (瘤白鳥)くちばしの基部に黒い瘤(こぶ)状の突起があることから。 (瘤白鳥)くちばしの基部に黒い瘤(こぶ)状の突起があることから。
 治水緑地にいてるコブハクチョウも、万博公園にいてるコブハクチョウもきれいやけど、怒ったら怖い。万博公園には親子でいたけど、治水緑地のコブハクチョウは1羽でいてる。お父さんが、野鳥じゃないって言ってるけど、そしたら、どこで飼われていたんやろ?ドバトも野鳥じゃないって言ってるけど、ようわからへんわ。 治水緑地にいてるコブハクチョウも、万博公園にいてるコブハクチョウもきれいやけど、怒ったら怖い。万博公園には親子でいたけど、治水緑地のコブハクチョウは1羽でいてる。お父さんが、野鳥じゃないって言ってるけど、そしたら、どこで飼われていたんやろ?ドバトも野鳥じゃないって言ってるけど、ようわからへんわ。
 |
| カイツブリ |
カイツブリ目カイツブリ科 L26 |

打上川治水緑地 |
|
小型(ムクドリ大)で、とがったくちばし。
湖沼や流れの緩い河川にすみ、北日本では冬に暖地に移動。ヨシなどの植物や杭を支えにして、水上に浮いたような巣をつくる。ひなにはしま模様。繁殖期にはキリリ…とけたたましく鳴く。
 (鳰)「カイ」は水を掻く、「ツブリ」は水に潜るときのズブリという音に由来。「ミズクグリ」「息長鳥」などの別名も。 (鳰)「カイ」は水を掻く、「ツブリ」は水に潜るときのズブリという音に由来。「ミズクグリ」「息長鳥」などの別名も。
※古名は鳰(にお)という。私たちの地域では「ジボ」という名で呼ばれているが、これも「にお」が転じたものでしょう。
 この鳥も校歌の中に出てくるけど、まだわりといてる。水の中にもぐって魚をとるけど、今度どこに浮かんでくるか分からないので、双眼鏡で追いかけるのが大変。巣は水の上に作るみたいやけど、本物は見たことがない。 この鳥も校歌の中に出てくるけど、まだわりといてる。水の中にもぐって魚をとるけど、今度どこに浮かんでくるか分からないので、双眼鏡で追いかけるのが大変。巣は水の上に作るみたいやけど、本物は見たことがない。
 |
| バン |
ツル目クイナ科 L32
|

打上川治水緑地 |
|
ハト大で額が赤く、くちばしの先が黄色。
河川や湖沼、水田など湿地で繁殖し、関東以南の湿地で越冬。近年、公園の池などで、人から餌をもらうものが増えた。泳ぐときは首を前後に振る(=オオバン)。クルルッと鳴く。
 (鷭)田の番をするという意。 (鷭)田の番をするという意。
 水の上でもも上手に泳ぐし、陸に上っても早く走れる。治水緑地で1年中見られる水鳥。治水緑地と隣の蔵王池で繁殖している。幼鳥は目立たへん色をしている。幼鳥は親鳥によく怒られている。 水の上でもも上手に泳ぐし、陸に上っても早く走れる。治水緑地で1年中見られる水鳥。治水緑地と隣の蔵王池で繁殖している。幼鳥は目立たへん色をしている。幼鳥は親鳥によく怒られている。
 |
| ヒドリガモ |
カモ目カモ科 L49  |

打上川治水緑地 |
|
ピューっと笛の音のような強い声で鳴く(雄)。
湖沼、河川、湾に飛来。くちばしは灰色で先が黒。雌は他のカモより赤みがある。腹がはっきりと白い(=オシドリ)。夜もよく鳴く。
 (緋鳥鴨)雄の頭部が赤栗色をしているので緋鳥(ヒドリ)。 (緋鳥鴨)雄の頭部が赤栗色をしているので緋鳥(ヒドリ)。
 冬になると、集団で大きな池にやってくる。オスは、ぴゅーぴゅーと、口笛を鳴らしたような大きな声なので、遠くからでもすぐに分かる。オスには、目の後ろが緑色のがいる。メスを見分けるのはとっても難しい。 冬になると、集団で大きな池にやってくる。オスは、ぴゅーぴゅーと、口笛を鳴らしたような大きな声なので、遠くからでもすぐに分かる。オスには、目の後ろが緑色のがいる。メスを見分けるのはとっても難しい。
 |
| アマサギ |
コウノトリ目サギ科 L50 |

穂谷川(淀川水系) |
|
白いサギでは最小。くちばしは夏も黄色。
水田や草地に飛来するが、暖地では冬を越すものもいる。他のサギより乾燥したところにもいる。冬羽は全身白くなり、チュウサギに似ているが小さく、首が短い。声はグァー。牛や耕作機の周りに群れて、飛び出す虫を狙う習性がある。
 (猩々鷺)夏羽が特有の美しい飴色をした鷺なので。 (猩々鷺)夏羽が特有の美しい飴色をした鷺なので。
 「見た目が尼さん(尼僧)っぽいので尼鷺かと思ってた。また、猩々鷺(別名)ってことは、一歩間違ってたらタヌキサギと呼ばれてたんか。」 「見た目が尼さん(尼僧)っぽいので尼鷺かと思ってた。また、猩々鷺(別名)ってことは、一歩間違ってたらタヌキサギと呼ばれてたんか。」
 アマサギって夏羽のイメージが強いから、もうちょっとでダイサギと間違えるとこやった。けど、やっぱり今度は夏羽を見たいです。 アマサギって夏羽のイメージが強いから、もうちょっとでダイサギと間違えるとこやった。けど、やっぱり今度は夏羽を見たいです。
 |
| カワセミ |
ブッポウソウ目カワセミ科 L17 |

打上川治水緑地 |
|
スズメ大、青い背、オレンジ色の腹。
北日本では秋冬に暖地に移動。河川や湖沼の枝や岩などにとまっていて、水面に飛び込んで、魚を取ったり水浴びもする(=ヤマセミ)。土の崖(がけ)の斜面に穴を掘って繁殖する。雄の下くちばしは赤い部分がない。チィーッと細く鋭く鳴く。
 (翡翠)川にすむソビ(カワセミの古名)から。 (翡翠)川にすむソビ(カワセミの古名)から。
 平成14年夏に、お世話になっている枚方市の鳥になりました。「飛ぶ宝石」といわれるけれど、意外と身近(住宅地)に多く、汚れた川を飛んでいると複雑な気持ちになります。 平成14年夏に、お世話になっている枚方市の鳥になりました。「飛ぶ宝石」といわれるけれど、意外と身近(住宅地)に多く、汚れた川を飛んでいると複雑な気持ちになります。
 チィーッって鳴いてまっすぐ飛んでくる。きれいやし、やっぱり人気モンやなあ。 チィーッって鳴いてまっすぐ飛んでくる。きれいやし、やっぱり人気モンやなあ。
 |
| イソシギ |
チドリ目シギ科 L20 |

打上川治水緑地 |
|
尻を上下に振り、チーリーリーと細く伸ばす声。
全国的のほぼ一年中、干潟や水田、湖沼、河川などあらゆる水辺で見られるシギ科はこの鳥だけで、1~2羽でいることが多い(北海道では夏鳥、沖縄では冬鳥)。スズメとムクドリの中間の大きさ。腹の白が肩先に切れ込んで見える。巣は草地に作る。
 (磯鷸)磯にいるシギなので (磯鷸)磯にいるシギなので
 シギって「鷸」と「鴫」、両方の字を充てているけれど、この辺の鳥は「鴫」かなぁ シギって「鷸」と「鴫」、両方の字を充てているけれど、この辺の鳥は「鴫」かなぁ
 餌を探してチョコチョコ歩き回っている姿が面白い。ハクセキレイによく追い払われているし、なんか気の弱そうな鳥やなぁ。 餌を探してチョコチョコ歩き回っている姿が面白い。ハクセキレイによく追い払われているし、なんか気の弱そうな鳥やなぁ。
 |
| コチドリ |
チドリ目チドリ科 L16 |

打上川治水緑地 |
|
スズメ大で黄色い足、目の周りに黄色い輪。
南日本では冬を越すものもあり、南西諸島では冬鳥だが、多くは九州以北の川原、海岸、干拓地に夏鳥として飛来。小石や砂の地上で繁殖する。冬羽は幼鳥のように淡い色になる。ピオとやさしい声で鳴き、繁殖期には飛びながらピッピッピッと続けて鳴く。
 (小千鳥)小型の千鳥なので (小千鳥)小型の千鳥なので
 TVで子育ての様子を見たことがあるけど、けがをしたふりをして敵を自分のほうに引きつけて、卵やひなを守る。小さい体やのに、すごいなあって思った。 TVで子育ての様子を見たことがあるけど、けがをしたふりをして敵を自分のほうに引きつけて、卵やひなを守る。小さい体やのに、すごいなあって思った。
 |
| ハクセキレイ |
スズメ目セキレイ科 L21 |

打上川治水緑地♂ |

打上川治水緑地♀ |
|
白いほお、澄んだ声。
広い河川、農耕地、市街地の空き地など開けた環境を好む。春夏は北日本に、秋冬は積雪のない地域に多い。チュチュン、チュチュンと鳴く(×セグロセキレイ)。雌は雄より黒味が乏しい。雄も冬羽の上面は淡くなる。西日本には、過眼線がない亜種がいる。
 (白鶺鴒)鶺鴒は背筋が伸びた清令な鳥のこと。顔が白いセキレイ。 (白鶺鴒)鶺鴒は背筋が伸びた清令な鳥のこと。顔が白いセキレイ。
 夏はセグロセキレイとの見分けが難しいけど、冬は楽チン!。お父さんが、国道沿いの大きな看板にねぐらがあったって言ってたけど、いっぺん見に行きたい。 夏はセグロセキレイとの見分けが難しいけど、冬は楽チン!。お父さんが、国道沿いの大きな看板にねぐらがあったって言ってたけど、いっぺん見に行きたい。
 |
| セグロセキレイ |
スズメ目セキレイ科 L21 |

打上川治水緑地 |
|
ジジッと濁った声。
九州以北の河川の中流、石の川原を好む。S澄んだ声も交えてジービチチロジージジと複雑に鳴く。日本特産種。
 (背黒鶺鴒)鶺鴒は背筋が伸びた清令な鳥のこと。背中が黒いセキレイ。 (背黒鶺鴒)鶺鴒は背筋が伸びた清令な鳥のこと。背中が黒いセキレイ。
 家の周りでは、ハクセキレイより数が少ないかな…。 家の周りでは、ハクセキレイより数が少ないかな…。
 |
| キセキレイ |
スズメ目セキレイ科 L20 |

打上川治水緑地 |
|
黄色い腹、澄んだ声。
屋久島以北の川や池沿いの地上にすみ、秋冬には南下するものもいる。チチン、チチンと鳴く。Sチチチチと細く鋭い声。
 (黄鶺鴒)鶺鴒は背筋が伸びた清令な鳥のこと。腹が黄色いセキレイ。 (黄鶺鴒)鶺鴒は背筋が伸びた清令な鳥のこと。腹が黄色いセキレイ。
 山の近くでしか見たことなかったけど、治水緑地にも飛んでくるって分かった。 山の近くでしか見たことなかったけど、治水緑地にも飛んでくるって分かった。
 |
| イソヒヨドリ |
スズメ目ツグミ科 L23 |

天野川河口 |
|
海岸の磯や堤防にすみ、ムクドリ大。
北日本では冬に暖地に移動。市街地のビル街で見られることもある。ジョウビタキのようにおじぎをして、尾を震わせる。ふわふわした飛び方。雄の若い鳥は雌に似ているが、次第に雄成鳥の色彩が加わる。ジジッと鳴く。Sツツピーコーと澄んだ声も(雌も)
 (磯鵯)磯に生息し、ヒヨドリに似た鳥であることから。 (磯鵯)磯に生息し、ヒヨドリに似た鳥であることから。
 青い鳥はカワセミしか見たことがなかったから、はじめはカワセミやと思った。けど、飛び方が違うかったから、もういっぺん双眼鏡で見なおしてイソヒヨドリやってわかった。 青い鳥はカワセミしか見たことがなかったから、はじめはカワセミやと思った。けど、飛び方が違うかったから、もういっぺん双眼鏡で見なおしてイソヒヨドリやってわかった。
 |
| シロハラ |
スズメ目ツグミ科 L24  |

大阪城公園 |
|
ツグミやアカハラに似て、腹が白っぽい。
西日本に比較的多く飛来。やぶのある暗い林の地上で、採食していることが多い。飛ぶと、尾の先の白が目立つ。アカハラに似た声で、キョッ、キョキョキョやツイーと鳴く。
 (白腹)腹の中央が白いので白腹。 (白腹)腹の中央が白いので白腹。
 ツグミと同じようなとこにいてるけど、数が少ない。スズメとエサの取り合いをしていた。 ツグミと同じようなとこにいてるけど、数が少ない。スズメとエサの取り合いをしていた。
 |
| カモメ |
チドリ目カモメ科 L45 W115  |

大阪城公園 |
|
ウミネコよりやや小さく、尾に黒帯がなく、背が淡い。
九州以北の海岸や河口に飛来。くちばしは黄色で、足も黄色っぽい。キュッキューキューなどと鳴く。
 (鴎)不明。カモメの"メ″はスズメと一緒で群れている鳥のことらしいですが…。 (鴎)不明。カモメの"メ″はスズメと一緒で群れている鳥のことらしいですが…。
 ユリカモメと比べて、目つきが鋭くて怖い…。ユリカモメみたいに淀川をあんまりのぼってけーへんし、数もすくないんちゃうかなぁ。 ユリカモメと比べて、目つきが鋭くて怖い…。ユリカモメみたいに淀川をあんまりのぼってけーへんし、数もすくないんちゃうかなぁ。

|
| ユリカモメ |
チドリ目カモメ科 L40 W92  |
|
|
カラスより小さめで細く、くちばしと足が赤い。
海岸のほか、河川や湖沼など、最も内陸まで飛来するカモメ。夏羽は頭部が黒褐色になる。若鳥は翼の上面や尾に黒い線がある。ギューイと高く濁った声。ほぼ同じサイズのミツユビカモメ(くちばしが黄色で、足は黒い)は沖にいることが多い。ズグロカモメ(くちばしが黒くて短い)は西日本の干潟に飛来するが、少ない。
 (百合鴎)入江のカモメが転じてユリカモメ。 (百合鴎)入江のカモメが転じてユリカモメ。
※主なカモメ類の見分けの目安
○一年中見られる
(中型)ウミネコ 黄色いくちばし(赤と黒の模様)と黄色い足
●秋から冬に見られる
(小型)ユリカモメ 赤いくちばしと赤い足
(中型)カモメ 黄色いくちばしと黄色い足
(大型)セグロカモメ 黄色いくちばしとピンクの足
 大阪城公園で観光客の人からエサをもらってた姿が、まるでドバトみたいやった…。 大阪城公園で観光客の人からエサをもらってた姿が、まるでドバトみたいやった…。
 |
| ヤマガラ |
スズメ目シジュウカラ科 L14 |

宮津市 |
|
胸から腹が赤みのある茶色
よく茂った広葉樹林を好む。シジュウカラより尾が短い。スィースィーとシジュウカラよりかすれた声やビービーと鼻にかかった声を出す。
Sシジュウカラより低い声でゆっくりしたテンポ。
 (山雀)山に住むカラなのでヤマガラ (山雀)山に住むカラなのでヤマガラ
 カラの仲間で茶色っぽいのはこの鳥だけなので、割と見つけやすい。淀川にもよくいる。 カラの仲間で茶色っぽいのはこの鳥だけなので、割と見つけやすい。淀川にもよくいる。
 |
| マガモ |
カモ目カモ科 ♂L59  |
|
|
くちばし全体が淡い黄色(雄)
北日本では繁殖するものもいるが、多くは冬鳥として湖沼、河川、海岸に飛来する。雌雄とも足は橙色、尾は白。エクリプスでも雄はくちばしが黄色っぽい。低い声でグァーとかクワッと鳴く。求愛時には笛のような声も出す。マガモを家禽として改良したのがアヒルなので、マガモによく似たアヒルが飼われていたり野生化していることもある。またカルガモとの交雑種(カルガモの特徴を合わせ持つ)を見られることがある。
 (真鴨)「真のカモ」の意 (真鴨)「真のカモ」の意
 治水緑地には、マガモとアオクビアヒルの両方がいてるけど、マガモはあんまり人からエサをもらっていないように思う。アオクビアヒルはちょっと太っている。 治水緑地には、マガモとアオクビアヒルの両方がいてるけど、マガモはあんまり人からエサをもらっていないように思う。アオクビアヒルはちょっと太っている。
 |
| ケリ |
チドリ目チドリ科 L36 |

近くの田んぼ(冬) |
|
ハト大で、黄色く長い足(飛翔時は尾の先を越えて出る)
主に関東以西の水田で繁殖し、積雪のある地域では秋冬に暖地に移動。河原や干潟で見られることもある。キリッ、キリッなどと鋭い声。
 (計里)キリッ(ケリ)、という鳴声から (計里)キリッ(ケリ)、という鳴声から
 うちが田んぼをしていたころはよく見かけたけど、今は田んぼが少なくなってあまり見かけなくなった。親戚のオッちゃんは「ケン」と呼んでいたけど、そう聞こえなくもないかなぁ。子育てのころは気が荒くて、お父さんも近づきすぎて、追っかけられていた。 うちが田んぼをしていたころはよく見かけたけど、今は田んぼが少なくなってあまり見かけなくなった。親戚のオッちゃんは「ケン」と呼んでいたけど、そう聞こえなくもないかなぁ。子育てのころは気が荒くて、お父さんも近づきすぎて、追っかけられていた。
夜も、あの特徴のある声を出しながら飛んでいるから、すぐ分かる。ゴイサギと一緒やな。
 |
| イカル |
スズメ目アトリ科 L23 |

寝屋川 |

20羽くらいの群れで… |
|
大きな黄色いくちばし。
九州以北の低山の林。小群れ見ることが多い。飛ぶと翼の白斑が帯になって見える。キョッ、キョッと鳴く。
Sキコキコキーなどと朗らかな澄んだ声。
 (鵤、斑鳩) 奈良県の斑鳩(いかるが)町に多いので、イカル。鳴声が「イカルコキ~」と聞こえるからという擬声語という説もある。 (鵤、斑鳩) 奈良県の斑鳩(いかるが)町に多いので、イカル。鳴声が「イカルコキ~」と聞こえるからという擬声語という説もある。
 体も大きくてぶっとい黄色いくちばしなので、いたらすぐ分かる。キーコーキーという鳴き声にも特徴があるしね。はじめて見たのは長野県の妙高高原やったから、山の鳥とばっかり思っていたら、地元の川にいたから何かうれしいやら、がっかりやらで…。まあええか 体も大きくてぶっとい黄色いくちばしなので、いたらすぐ分かる。キーコーキーという鳴き声にも特徴があるしね。はじめて見たのは長野県の妙高高原やったから、山の鳥とばっかり思っていたら、地元の川にいたから何かうれしいやら、がっかりやらで…。まあええか
 |
| エナガ |
スズメ目エナガ科 L14 |

奈良・平城宮跡 |
|
白っぽい小さな体に長い尾
九州以北の低山の林。チーという細い声はシジュウカラ科に似ているがツリュリュという声は独特。北海道の亜種シマエナガは顔に模様がない。コケを使った球形の巣を枝にかける。秋冬はシジュウカラ科の鳥と群れる。
 (柄長)長い尾が柄杓(ひしゃく)の柄(え)に似ているので、エナガ (柄長)長い尾が柄杓(ひしゃく)の柄(え)に似ているので、エナガ
 エナガを見る時は、いつもシュジュウカラやコゲラ一緒。綿みたいにフワフワしていて、尾っぽが長くって、目が小さくてかわいい。 エナガを見る時は、いつもシュジュウカラやコゲラ一緒。綿みたいにフワフワしていて、尾っぽが長くって、目が小さくてかわいい。
 |
(記号の説明)  夏鳥 夏鳥  冬鳥 冬鳥  こうたろうの感想 こうたろうの感想  お父さんの感想 お父さんの感想
L くちばしの先から尾の先までの全長(CM)
W 翼を広げたときの長さ(CM)
S さえずりの声(地鳴きとの区別がはっきりしている場合のみ)
| 用語 |
説明 |
| エクリプス |
カモ類のオスに見られる羽色で、繁殖期の後に全身の体羽が抜け変ってなるメスに似た羽色になる。
エクリプスは日食や月食などの「星食」を意味する言葉で「光を失う」ことが語源 |
| 求愛給餌 |
ペアの雄が雌に食物をプレゼントすること。シジュウカラ科、アトリ科、モズ科、カワセミ科などに見られる |
参考図書「野鳥観察ハンディ図鑑 新山野の鳥・新水辺の鳥」(日本野鳥の会)
「今日からはじめるバードウォッチング」(日本野鳥の会)
「野鳥ガイド」(新星出版社)
「バードウォッチング入門」(文一総合出版)
「日本の野鳥羽根図鑑」(世界文化社)
「日本の野鳥」(小学館)
「ヤマケイポケットガイド⑦ 野鳥」(山と渓谷社)
「広辞苑」(岩波書店)
|